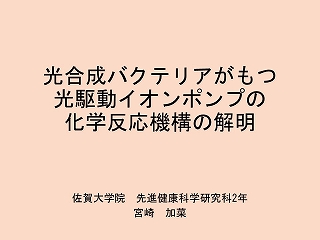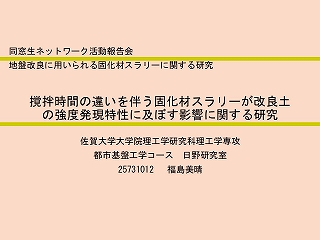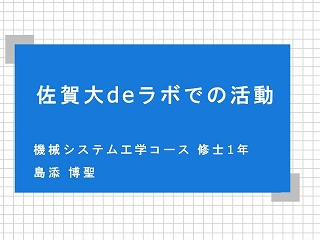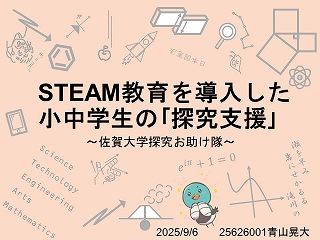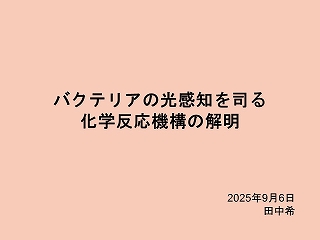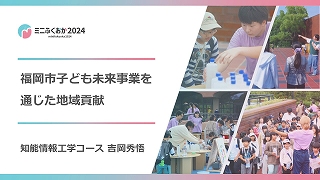2025同窓生ネットワーク活動報告会
update: 2025.09.13
2025年9月6日(土)、理工学部6号館において、菱実会定例総会の一つとして同窓生ネットワーク活動報告会が開催されました。
6名の学生(大学院生)の方々に大学における活動や研究等を発表していただきました。この試みは、これからの菱実会総会の有り方を改善し、単なる同窓生だけの同窓会にとどまらず、在学生、卒業生、理工学部教職員、そして企業を繋ぐこともできますので、大学の将来作りにも貢献できると確信しております。
なお、座長は田中稲穂氏と吉岡秀悟氏に務めていただきました。
*右画像をクリックすると、各発表のPDFがご覧になれます。
(1) 光合成バクテリアがもつ光駆動イオンポンプの化学反応機構の解明
氏名: 宮崎 加菜 氏(生化R02入)
所属: 先進健康科学研究科 健康機能分子科学コース2年
発表概要: 微生物も植物のように,光を利用した化学エネルギー生産の仕組みを備えている。その代表例が光を吸収してイオンを輸送する光応答性のタンパク質群である。このような光応答性タンパク質のなかで,近年発見された1つが光合成バクテリアのMastigocladopsis repensが持つ光駆動型Cl-ポンプ(MrHR)である。MrHRがイオンを輸送する光化学反応はこれまで不明であったが,低温・近赤外ラマン分光法という方法を用いてMrHRの具体的な反応機構を見出した。
(2) 地盤改良に用いられる固化材スラリーに関する研究
氏名: 福島 美晴 氏(都市R03入)
所属: 理工学研究科都市基盤工学コース1年
発表概要: 佐賀低平地は軟弱地盤が広く分布している。当地の地盤改良で多用されている深層混合処理工法では,ミキサーとアジテータにおいて固化材と水を撹拌してスラリー化し撹拌翼の先端から吐出,現地の土と混合することによって柱状改良体を築造する。本研究では,撹拌時間の違いを伴う固化材スラリーを用いた配合試験,熱分析を行い,固化材スラリーの撹拌時間が改良土の強度発現特性に及ぼす影響について検討した。
(3) 佐賀大deラボでの活動
氏名: 島添 博聖 氏(メカR03入)
所属: 理工学研究科機械システム工学コース1年
発表概要: 私は学部2年次から佐賀県内企業(株)中山HDと佐賀大学の産学官連携施設「佐賀大deラボ」に所属し,学生主体による施設運営と研究活動に従事してきました。県内外の行政機関・中山HDからの委託プロジェクト,学生主導のプロジェクト,展示会での出展など,多様な形態で3年間技術開発に取り組みました。学生が主体的にアイデアを創出し,実践的な社会実装教育を通じて技術開発に取り組む本施設の運営と具体的な活動内容について報告します。
(4) STEAM教育を導入した小中学生の「探究活動」支援
氏名: 青山 晃大 氏(応化R03入)
所属: 先進健康科学研究科 健康機能分子科学コース1年
発表概要: 2023年に佐賀大学で結成した児童生徒の「探究活動」の支援を中心に行う課外活動チーム「佐賀大学探究お助け隊」。文系・理系を問わない視点から「STEAM教育」を導入。佐賀の未来を創る志高い人の育成を掲げ,地域の工作教室や附属中学校での探究活動支援,小中学生向けの科学イベント「サイエンスカフェ」の企画運営を行った。本報告会では,「佐賀大学探究お助け隊」での取り組みを紹介し,その成果と課題について発表する。
(5) バクテリアの光感知を司る化学反応機構の解明
氏名: 田中 希 氏(生化R03入)
所属: 就職
発表概要: バクテリアのような微生物にも,動物と同様の光センサータンパク質が存在することが知られている。その代表例にセンサリーロドプシンⅡ(SRⅡ)があり,このタンパク質が光感知を実現するための光化学反応の仕組みがかねてから研究されてきた。卒業研究において近赤外ラマン分光法をいう手法を用いてSRⅡを研究した結果,30年以上受け入れられてきた定説を覆す実験結果を得て正しい反応機構を報告した。
(6) 福岡市子ども未来事業を通じた地域貢献
氏名: 吉岡 秀悟 氏(知能R03入)
所属: 理工学研究科 知能情報工学コース1年
発表概要: 「子どもがつくるまち ミニふくおか」は,子どもの主体性・協働性・コミュニケーション力を育み,福岡市の未来を創造的に切り開く人材の育成を目的とした事業である。2012年度から続くこの事業は,13回目の開催となる「ミニふくおか2024」より,私たち25歳以下の若者で構成される「ユースプロジェクト」が主体となり,事業を企画・運営する新体制へと移行した。今後は,「ミニふくおか2024」での経験を活かし,ユースプロジェクトの継続と発展に貢献したい。